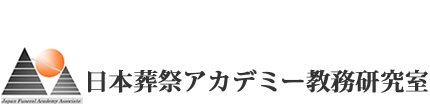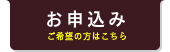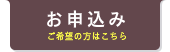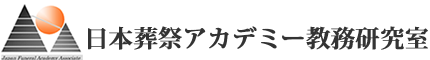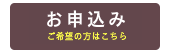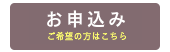死化粧(しにけしょう)
映画「おくりびと」で一躍有名?になった、「死に化粧」ではあるが、これは納棺を専門とするいわゆる「納棺師」と重なる。遺体の修復や清浄(湯かん)に加えて化粧もする。
地域によっては、身近な遺族の手で行われていた習俗でもあった。それが葬儀社の遺族サービスとしてオプション提供され、その後専業化した経緯がある。専業化の例では、病院から寝台自動車での搬送や火葬場への霊柩車のように、葬儀社からの委託で行なわれる部門的な専門業種として個別化ものがある。
死化粧も元看護士さんなどが「エンゼルメイク」という名称で起業化し、ケア・サービスとして、専属的に葬儀社からの依頼を受けているところもある。
話を聞くと、
『長期入院や病状から変化した死に顔を、できる限り生前の本人らしく、また眠るような姿になるよう、配慮している』
とのこと。確かに安らかな死に顔は遺族を安心させるものだと思う。
ただ、古来の葬送文化と少しかけ離れた現代的な遺体観かもしれない。本来、生者と死者は当然ながら区別されるべき存在で、特に日本では遺体は、隔離・隔絶・封印することが葬法の基本でもあった。
「死」に対しての「畏怖」は、魂に対して畏れ敬い、亡骸に対しては恐怖してきた経緯がある。死体は習俗上では普通に忌避すべき穢れ感の塊であった。だからこれを遠ざけた。
死者を生者のように「見せる」ことに自分の違和感があるのは、その深層があるからかもしれない。
死化粧や死装束は、死者を死者「らしく」させることが目的で、生前のように見せかけることではない。
本来は、死に顔を拝して、その形相や顔色から命の枯渇を感じ取った。出来れば見たくはない。でも見ざるを得ない場合もある。特に身近な人や親しい人は、そこに「決別」があったのかもしれない。どうにかして生者に近づけようとするのか、死生観が安易になってしまったのか、疑問を残す。
死者の顔には相変わらず白布をかける習俗は顕在する。その下に「元気そうな化粧」をされた顔があると思うと居たたまれない。